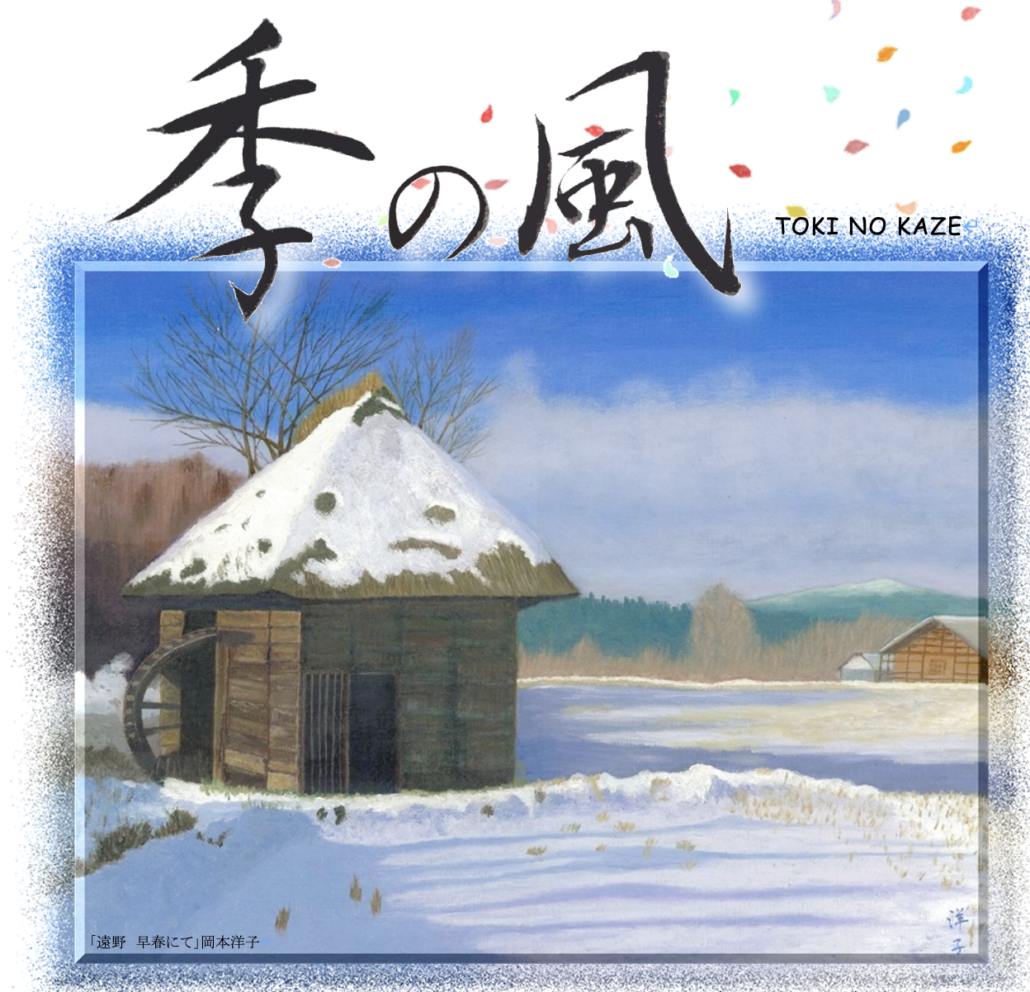9月20日からは「秋のお彼岸」。ご先祖様を偲び、感謝を伝えるこの季節──
福壽堂秀信では、関西ならではの「彼岸団子」をご用意しております。
お彼岸とは?
「彼岸」とは、仏教で説かれる“悟りの世界”──すなわち煩悩や迷いを離れた理想の境地を指す言葉です。
それに対し、私たちが暮らすこの現実世界は「此岸(しがん)」と呼ばれます。
お彼岸は、春分・秋分の日を中心に、前後3日ずつを合わせた7日間を指します。
昼と夜の長さが等しくなるこの時期、太陽が真西に沈むことから、極楽浄土があるとされる「西方」にもっとも近づくと信じられてきました。
こうした自然現象と仏教思想が結びついたことで、日本では先祖供養や墓参りの習慣として定着し、今も多くの家庭で大切に受け継がれています。
静かに手を合わせ、ご先祖様に感謝の気持ちを伝える──
お彼岸は、日本ならではの“祈りの季節”ともいえるでしょう。
お彼岸に彼岸団子を食べる理由
お彼岸には、お墓参りや仏壇へのお供えに、団子や餅菓子を用いるのが古くからの風習です。
団子の丸いかたちは「円満」や「調和」を象徴し、仏さまやご先祖様への敬意と感謝のこころを表します。
また、白い餅と餡には「邪気祓い」「厄除け」の意味合いも込められており、家族の無事を願う行いとして受け継がれてきました。
福壽堂秀信では、この大切な行事にふさわしい彼岸団子を、こし餡・粒餡の二種類でご用意しております。
いずれも丁寧に炊き上げた自家製餡を使用し、さらりとした口当たりと控えめな甘さが特長です。
ご家庭での静かなひとときや、お供えものとしてもご好評をいただいております。
『おはぎ(お萩)』と『ぼたもち(牡丹餅)』の違いとは?
「おはぎ」と「ぼたもち」は、どちらも同じ餅菓子を指します。
春は牡丹にちなみ「ぼたもち」、秋は萩にちなみ「おはぎ」と呼ばれるようになった、季節の呼び名の違いによるものです。
福壽堂秀信では、関西圏の文化に根ざした表現として、あえて「彼岸団子」としてご紹介しております。
▶ 季節による呼び分けの由来については、
同志社女子大学・日本語日本文学科 教授によるコラム
でも詳しく紹介されています。

※帝塚山本店の陳列画像です。
商品情報
- 商品名: 彼岸団子(こし餡/粒餡)
- 価格: 各1ケ 260円(税込)
- 販売期間: 9月20日(土)〜23日(火・祝)
- お日持ち: 当日中
- ※数量限定販売、完売の際はご容赦ください。
お彼岸は、静かに心を整え、ご先祖様への感謝をかたちにして伝える機会でもあります。
団子や和菓子を通して、日本の四季や伝統を感じながら過ごす時間──
ご家族やご親戚との語らいの場に、福壽堂秀信の和菓子がお役立ていただければ幸いです。

 オンラインショップ
オンラインショップ