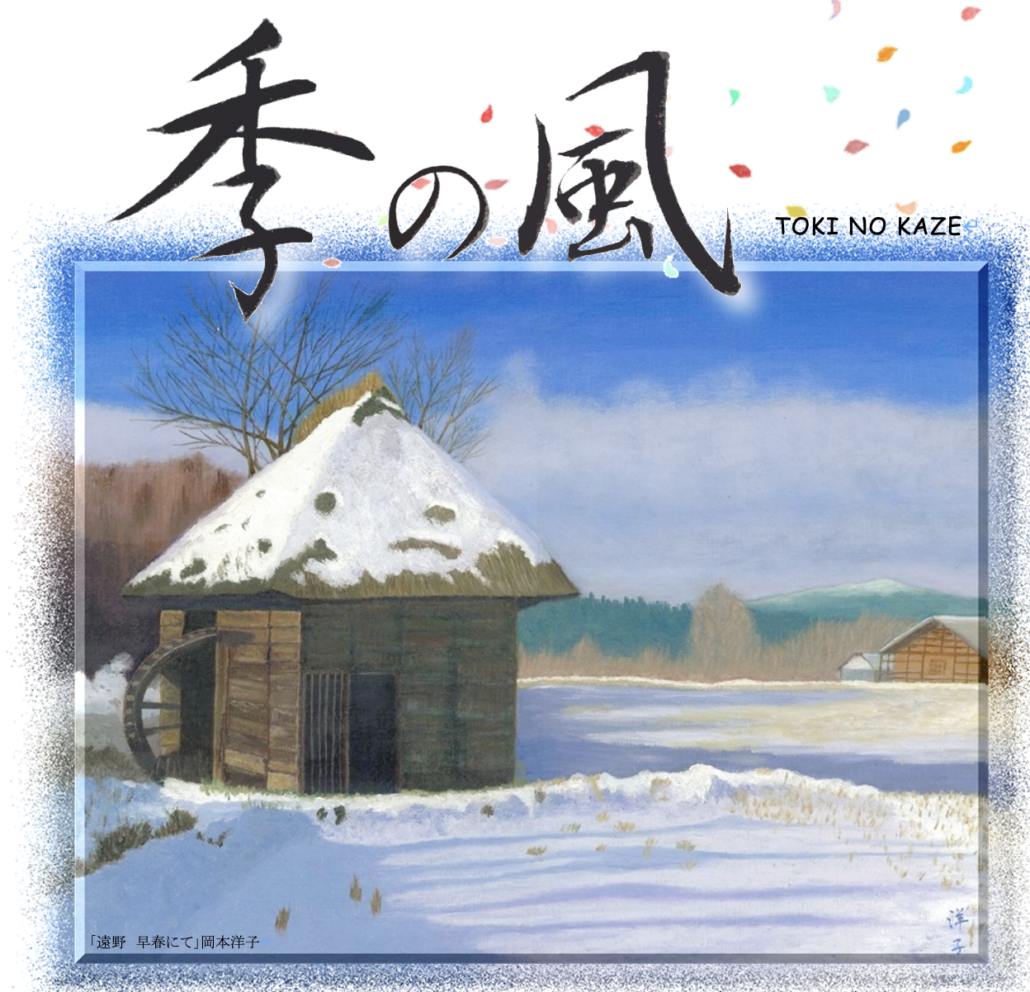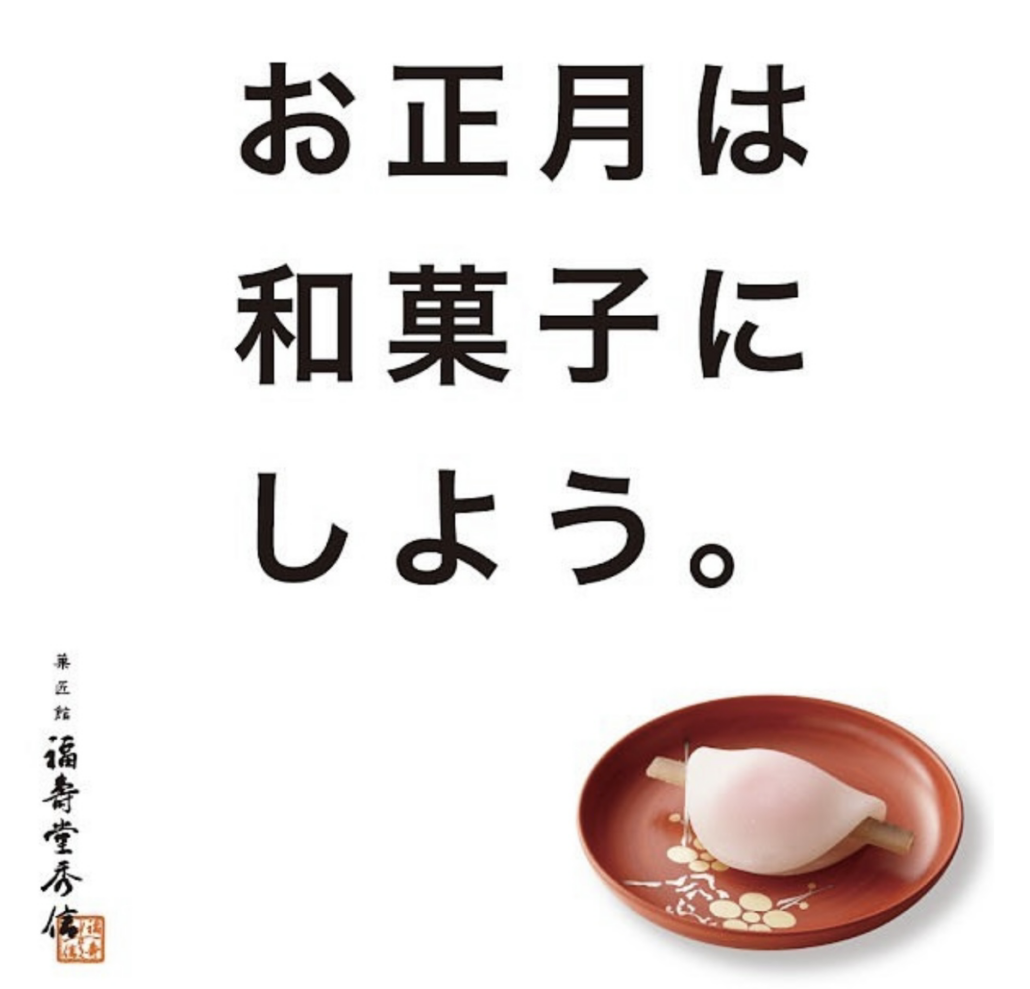苞(つと)という言葉に込められた意味
「苞(つと)」という言葉には、山から持ち帰る土産物という意味があります。
山の恵みをそっと包み、大切な誰かに手渡す──
そのような日本人の所作と季節感を映した言葉といえるでしょう。
福壽堂秀信の「山の苞」は、そうした古い日本の感性を手本に、秋の自然をかたちにした和菓子です。

これも和菓子?──本物に見まごうかたちと質感
竹籠にそっと納められた、柿、あけび、みかん、栗、松茸。
一見すると、どれも果物や山の幸そのものですが、実はすべて和菓子でできています。
- 栗・あけび:焼き菓子
- 柿・松茸・みかん:薯蕷(じょうよ)饅頭
精巧なかたちと色合いに目を奪われがちですが、味わいもまた和菓子の伝統に裏打ちされたもの。
やさしい甘みと秋らしい香りに、口にして初めて気づく「もう一つの美しさ」が宿ります。
製造の様子──やさしく、確かに、かたちづくられる

「山の苞」に使われている薯蕷饅頭は、山芋を練り込んだ生地を用いた菓子です。
この生地は粘りが強く扱いが難しいため、長年の経験に基づく力加減が求められます。
強すぎれば形が崩れ、弱すぎれば蒸し上がりにくい。
職人は完成形を思い浮かべながら、手際よく、やさしく形づくっていきます。

こうした工程の一つひとつに、和菓子づくりの繊細な技と感性が息づいています。
色とかたち──目に見える「観察の美」


本物の果実や山の幸をよく観察し、かたちだけでなく、表面の質感や色のグラデーションまで丁寧に再現しています。
柿のへたの角度、みかんの細やかな凹凸、松茸の軸の表情──
それぞれが、職人の「見つめる力」と「手の記憶」によって和菓子という小宇宙に落とし込まれています。
同じものはふたつとありません。
一つひとつが、自然を映す写し絵のようでもあり、小さな工芸品のようでもあります。



工芸菓子の歴史──和菓子が芸術になるとき
和菓子は、味わうだけでなく、目でも楽しむ文化を育んできました。
なかでも「工芸菓子」と呼ばれる菓子は、写実性や美的表現を極限まで追求し、
そのかたちをもって四季や風物を映し出す、まさに“食べられる芸術”といえます。
その起源は、江戸時代の上菓子(じょうがし)にあり、茶の湯の席や大名家への献上品として発展してきました。
明治以降は職人技術の競技会が各地で行われるようになり、やがて工芸菓子は「観るための和菓子」として独自の地位を築いていきます。
現代では、全国和菓子協会主催の大会などでその技術が披露され、工芸菓子は文化財的な存在としても位置付けられています。
こうした背景のもとに、当店の「山の苞」も生まれました。
工芸菓子の写実的な美しさと、生菓子としての味わいを両立させる──その想いが、一つひとつの造形に込められています。
参考リンク:
▶ 詳しくはこちら
山の苞──お包みのかたちによるふたつのご用意
桧葉(ひば)タイプ *お日持ち:2日間
竹かごの中に桧葉を敷き、その上に和菓子を盛りつけたもの。
短い日持ちではありますが、見た目の趣深さは格別。
手渡しの贈り物や、季節を感じる集まりに好まれています。


パックタイプ *お日持ち:約5日間
桧葉の代わりに敷紙を使い、外装をパックで整えた仕様。
保護性が高く、遠方への配送にも対応しています。
あたたかな気持ちを届けたい方に向けて選ばれるかたちです。


お求めはオンラインショップまたは各店にて承ります。
▶ オンラインショップで購入する
▶ 店舗情報はこちら
※完全受注製造となりますため、各店舗でお求めの場合は4~5日前までにご予約願います。
見て驚き、味わって深く感じる──和菓子の醍醐味
「山の苞」は、本物そっくりを競う工芸菓子の要素を生菓子に生かした、弊店独自の季節菓子でございます。
ふたを開けてまず姿かたちに驚き、そして秋の郷愁を感じながら、口にして本物の味わいを楽しんでいただく──
和菓子の醍醐味をすべて詰め込んだ、自信をもってお届けする一品です。
他に似たもののない菓子を求める方へ。
ぜひ一度、「山の苞」の世界に触れてみてください。

 オンラインショップ
オンラインショップ