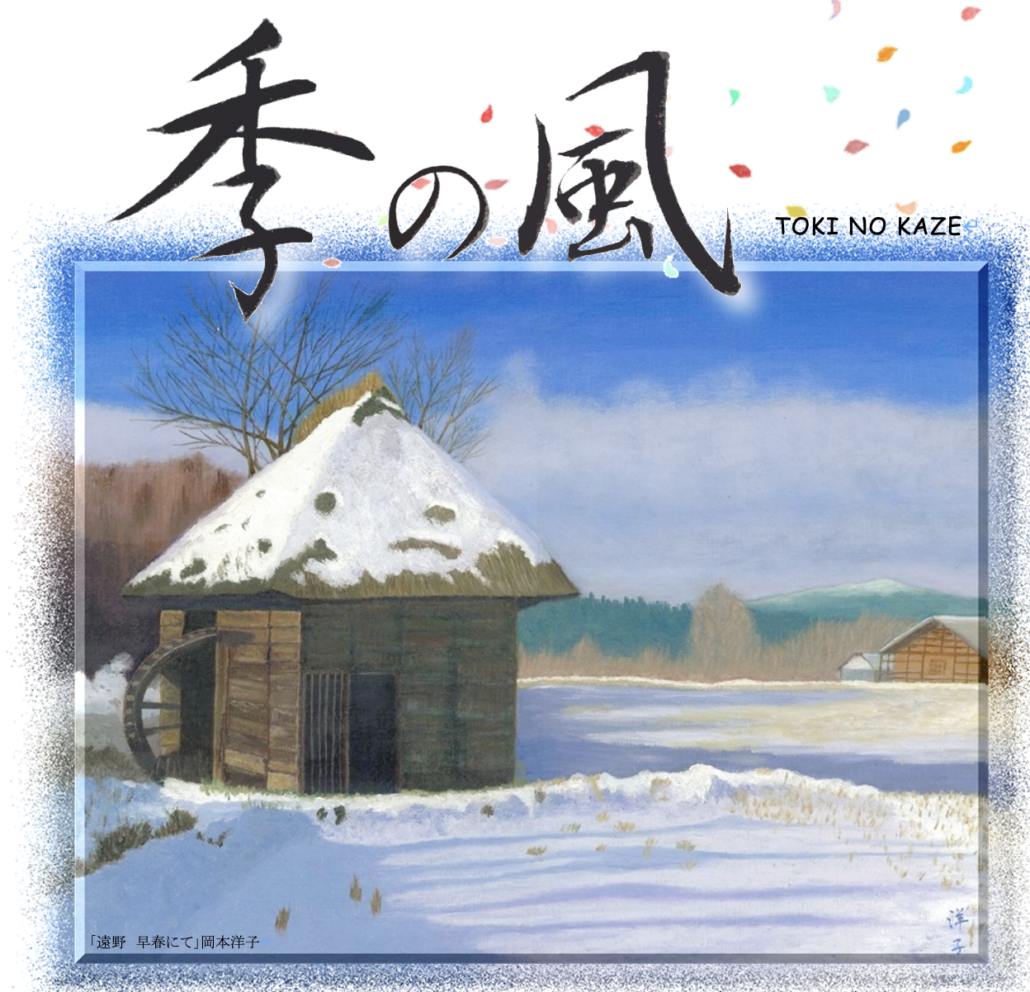寒い季節に恋しくなる、あたたかな甘味――「おぜんざい」と「お汁粉」。
関西と関東での呼び方の違い、あんの種類、汁気の有無など、地域文化や歴史的背景が映し出されるこれらの和菓子には、甘さ以上の深い味わいが宿っています。
おぜんざい・お汁粉とは?──言葉の背景と地域のちがい
「ぜんざい(善哉)」という言葉は、室町時代の出雲地方で振る舞われていた「神在餅(じんざいもち)」に由来すると言われています。僧侶がこれを食した際、「善哉(よきかな)此の汁」と喜んだことから、「ぜんざい」という言葉が生まれたという逸話もあります。仏教の法悦の言葉「善哉」にちなむ説です。
一方、「お汁粉(おしるこ)」という言葉は、江戸時代にはすでに文献に見られる呼び名で、小豆あんを汁状にし、焼き餅や白玉を加えた甘味を指します。関東ではこの「おしるこ」という表現が定着しており、汁気が多めであることが一般的です。
この記事では、こうした背景を踏まえながら、「ぜんざい/おぜんざい」と「お汁粉」の違いを見ていきます。
どう違う?──汁気・あんの種類・呼び名の差
「おぜんざい」と「お汁粉」の違いには、いくつかの視点がありますが、代表的な違いは次の3点です。
1. 汁気の多さ
関東では、汁気の多い小豆あんの甘味を「おしるこ」と呼び、粒あん・こしあんの区別にかかわらず広く使われます。一方、「ぜんざい」は汁気が少なく、餡そのものの濃さを楽しむスタイルを指すことが多いです。
関西では「つぶあんの汁もの=ぜんざい」、「こしあんの汁もの=おしるこ」と、汁気よりもあんの種類によって呼び名が変わるのが一般的です。このため、汁の多寡ではなく“あんの違い”での分類になります。
2. あんの種類
関西圏では、粒あんを煮溶かして小豆の形が残るものを「ぜんざい」、こしあんでなめらかに仕立てたものを「おしるこ」とする傾向があります。百貨店の和菓子売場などでも、この区分が目立ちます。ただし、店舗や家庭によって柔軟に運用されているのが実情です。
3. 地域ごとの呼び方
同じような材料でも、地域によって呼び名や形態が変わるのも「ぜんざい」の特徴です。たとえば沖縄では、甘く煮た金時豆と白玉、そしてかき氷を組み合わせた冷たい「ぜんざい」が定番であり、本州の「温かい甘味」とはまったく異なる文化が根付いています。
また、近畿地方や中部では、汁気の少ない餡餅のような甘味を「亀山」や「金時」と呼ぶこともあり、これは関東ではあまり使われない呼称です。
このように、「おぜんざい」や「お汁粉」という言葉の裏には、歴史・文化・風土が反映されています。どれも甘くて温かい小豆の味わいを楽しむものですが、呼び方やスタイルには、その土地ならではの風情が息づいています。
参考・出典
福壽堂秀信の「おぜんざい」── 澄みきった蜜に宿る職人の技
福壽堂秀信のおぜんざいは、まずその見た目に静かな驚きがあります。
澄みきった蜜に、ふっくらと炊き上げた小豆が浮かぶ佇まい。
一粒一粒の輪郭が崩れることなく、ほのかな光をまとって湯気を立てる姿は、まさに冬の余白にやさしく灯る和の甘さです。
小豆は、大粒のものだけを選りすぐり、皮を割らぬように、火加減を細やかに調整しながら炊き上げます。
時間をかけて、決して急がず、数日にわたり職人が見守るように仕上げるため、豆の食感と蜜の清らかさが損なわれません。
一見すると、透明な蜜の中に小豆をそっと沈めただけのように見えます。しかし、その蜜にはしっかりと小豆の風味が息づいており、ひと口含むと、豆と蜜がそっと溶け合い、上品な余韻が口中に広がります。
「甘さで包む」のではなく、素材の持つ力と職人の技が重なりあう、滋味深いひと椀です。

じっくりと、ただ静かに。
蜜を染み込ませながら、豆がやわらかく息づく瞬間を見極める。
手をかけすぎず、しかし手を離さない──そんな職人の姿勢が、この一椀に宿っています。
電子レンジで温めれば、湯気の立つ出来たてのような味わいを、気負わず楽しめるのも魅力です。
ご自宅でも、心ほどけるような温もりを味わっていただけます。
また、一部店舗では、栗の甘露煮を丸ごと一粒入れた「栗ぜんざい」もご用意しております。
秋から冬へと移る季節、ほっくりとした栗の甘さが、小豆の風味に寄り添う贅沢な一杯です。

秋から冬へ──食べ比べてみませんか、東西のおぜんざい文化
風が冷たくなり、ぬくもりが恋しくなる季節。
そんな秋から冬にかけて、「おぜんざい」や「お汁粉」は、心も体もやさしく包んでくれる甘味です。
関東では、さらりとしたこしあんの汁に白玉を浮かべて。
関西では、ふっくら炊いた粒あんにお餅を添えて汁気控えめに──
ひとくちに「おぜんざい」と言っても、地域ごとに異なる個性が楽しめるのは、日本ならではの食文化の豊かさかもしれません。
今年は、東西の味を比べながら、あたたかな椀の向こうに広がるそれぞれの風土や歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
小豆の滋味がそっと語りかけてくる、そんなひとときをぜひご自宅で。

 オンラインショップ
オンラインショップ