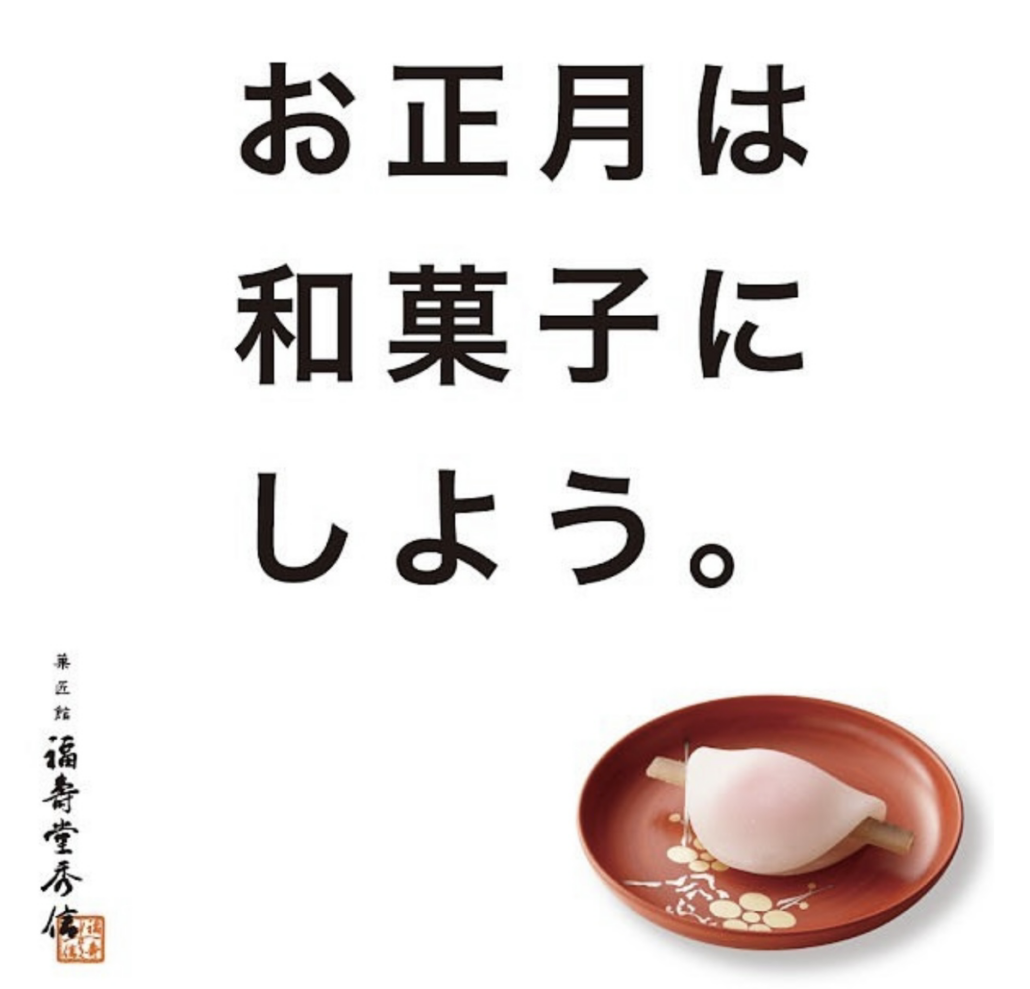6月16日は「和菓子の日」──橘に込めた思い
6月16日は「和菓子の日」。平安の昔から、和菓子には「無病息災」や「招福除災」の願いが込められてきました。福壽堂秀信では、今年もその日にあわせて、和菓子のはじまりとされる果実「橘(たちばな)」をかたどった上生菓子をご用意しました。
和菓子の日の由来──嘉祥の祝
西暦848年(嘉祥元年)、仁明天皇が「嘉祥」と改元し、6月16日に神前へ16個の菓子や餅を供えて、疫病退散と健康招福を祈願された故事に由来します。以来、宮中や武家社会、庶民の間でも「嘉祥の日」として、菓子を贈り合う習わしが続きました。
この伝統を現代に伝えるため、全国和菓子協会が制定したのが「和菓子の日」です。詳しくは、公式サイトの特集ページをご覧ください。
▶ 解説ページ:全国和菓子協会「和菓子の日」について
毎年6月16日、私たちは和菓子に込められた日本人の祈りと感謝の心にあらためて触れる機会を持ちます。
「橘」──和菓子のはじまりとされる果実
和菓子のルーツとされる果実──それが「橘(たちばな)」です。その起源は、古代・垂仁天皇の御代にさかのぼります。
天皇は、不老不死の理想郷とされる「常世(とこよ)の国」にある「非時香菓(ときじくのかぐのこのみ)」を求め、家臣・田道間守(たじまもり)に探索を命じました(※『日本書紀』では「田道間守」、『古事記』では「多遅摩毛理」と表記)。この果実は「時を定めず実り、黄金に輝き、食すれば年を取らず死なない」と伝えられていました。
田道間守は艱難辛苦の航海を越え、十年後ついに果実を持ち帰りますが、その時すでに天皇は崩御されており、彼は深く悲しみ、半分を皇后へ、残りを天皇の御陵に捧げ、涙ながらに使命を果たしたことを報告。その直後、彼自身も命を落としたと伝えられています。
この果実が後に「橘(たちばな)」であったとされ、『日本書紀』では「香菓(こうか)」と記述。当時「菓」は果物を指し、後に和菓子へと意味が展開された背景から、田道間守は「菓子業の祖神」として広く信仰されるようになりました。
なお「非時香菓」の表記・読み方については、文献や学術的立場によってさまざまありますが、私たち和菓子の世界では「非時香菓(ときじくのかぐのこのみ)」が一般的な表現として伝えられています。
和歌山県には、田道間守を祀る橘本神社があり、かつて白河法皇の熊野行幸において通夜の場ともなった壮麗な社です。この神社は、熊野九十九王子の中でも古社とされ、菓子と文化の守護神として全国から崇敬を集めています。
特に注目されるのが、毎年4月3日に行われる「全国銘菓奉献祭(菓子祭)」。全国150社以上の和菓子業者が銘菓を奉納し、「橘」を介した文化の継承が今も続いています。また、10月10日には「みかん祭」が盛大に開催され、柑橘の神としての田道間守を讃える行事として、多くの参拝者で賑わいます。
この神社の近くには、「橘」が初めて移植されたと伝えられる「六本樹の丘(みかん発祥の地)」も現存しており、日本における柑橘文化と和菓子文化の原点が重なり合う貴重な場所です。
また、『万葉集』や元明天皇、桓武天皇の記述にも「橘」は度々登場し、文化の象徴とされました。昭和12年に制定された文化勲章の意匠にも「橘」が採用されており、橘=文化の象徴という意味合いが今も息づいています。
奈良県奈良市の宝来山古墳は垂仁天皇の御陵とされ、そのそばの小島が田道間守の墓と伝わります。秋になると、橘の祖ともいえるミカンの木が黄金色に実り、歴史と信仰、和菓子の原点が静かに交差する場所となっています。
「さつき待つ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする」──古歌にも詠まれた橘は、故人への思慕や文化への敬意を象徴する果実でもあるのです。
6月16日の「和菓子の日」には、こうした「橘」の物語に想いを馳せ、和菓子とともに日本文化の源流を味わってみてはいかがでしょうか。
▶ 関連:奈良県:万葉のふるさと
上生菓子「橘」に込めた想い
福壽堂秀信では、この「和菓子の日」にあわせて、橘をかたどった上生菓子をご用意いたしました。柑橘の実を模した黄色の練り切りに、みずみずしい青葉を添え、心と体の平穏を願う意匠です。
古来より、橘は病を避け、幸せをもたらす果実とされてきました。この菓子に込めた想いを感じながら、ご家族や大切な方とともに「和菓子の日」をお楽しみください。
おわりに
和菓子は、ただの甘味ではなく、文化と祈りのかたちです。6月16日、「和菓子の日」に、季節の上生菓子「橘」を囲み、健やかなひとときをお過ごしください。

 オンラインショップ
オンラインショップ